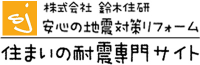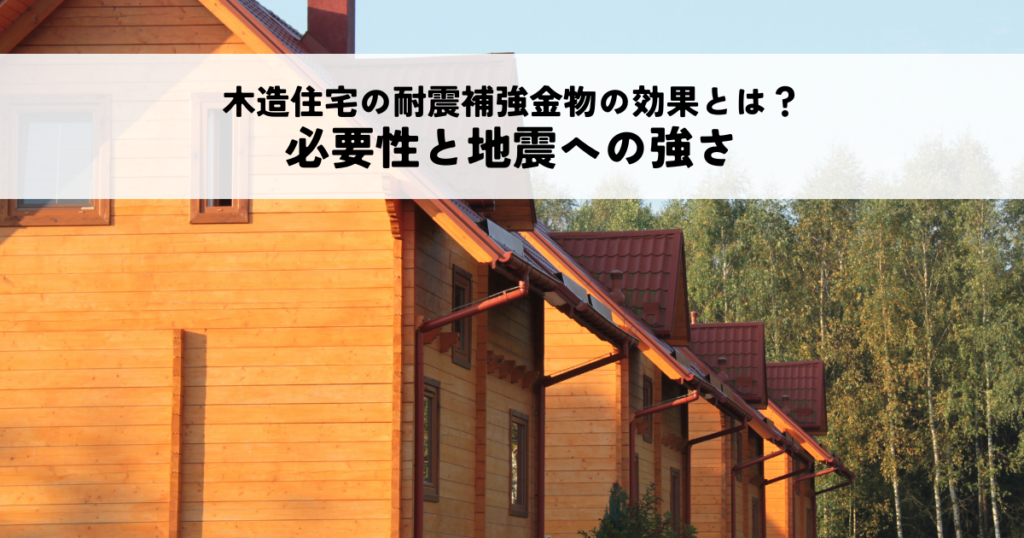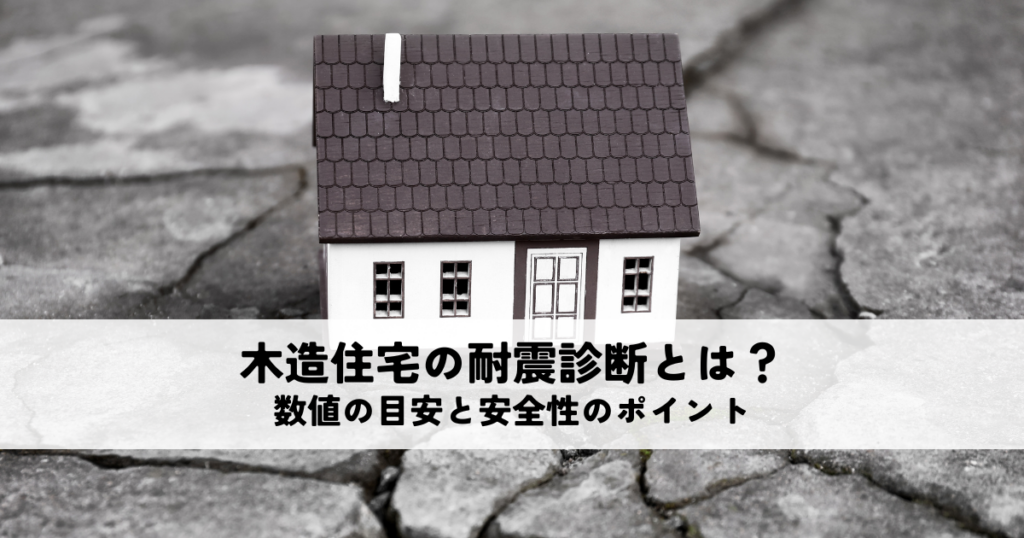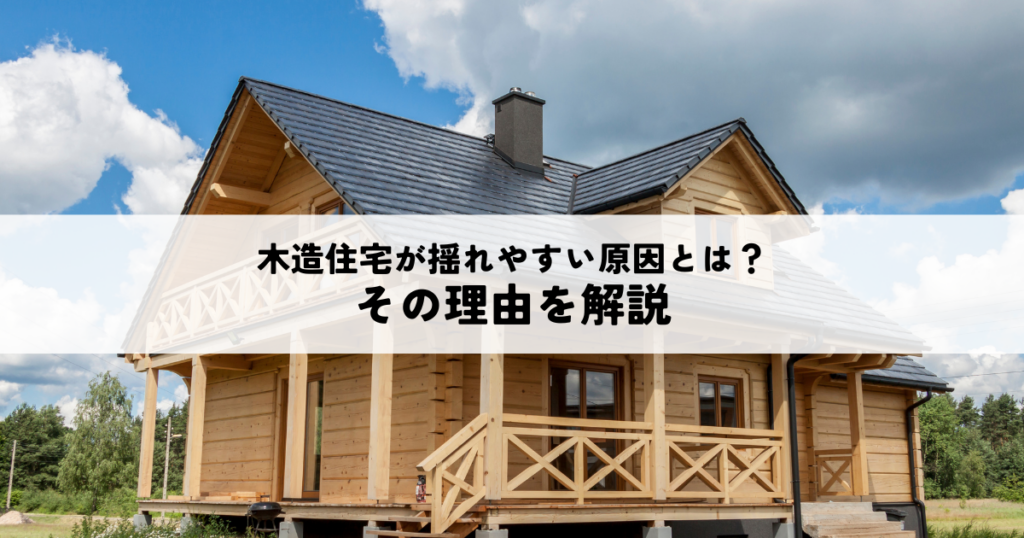耐震コラム
新耐震基準いつから?旧基準との構造上の違いを分かりやすく解説
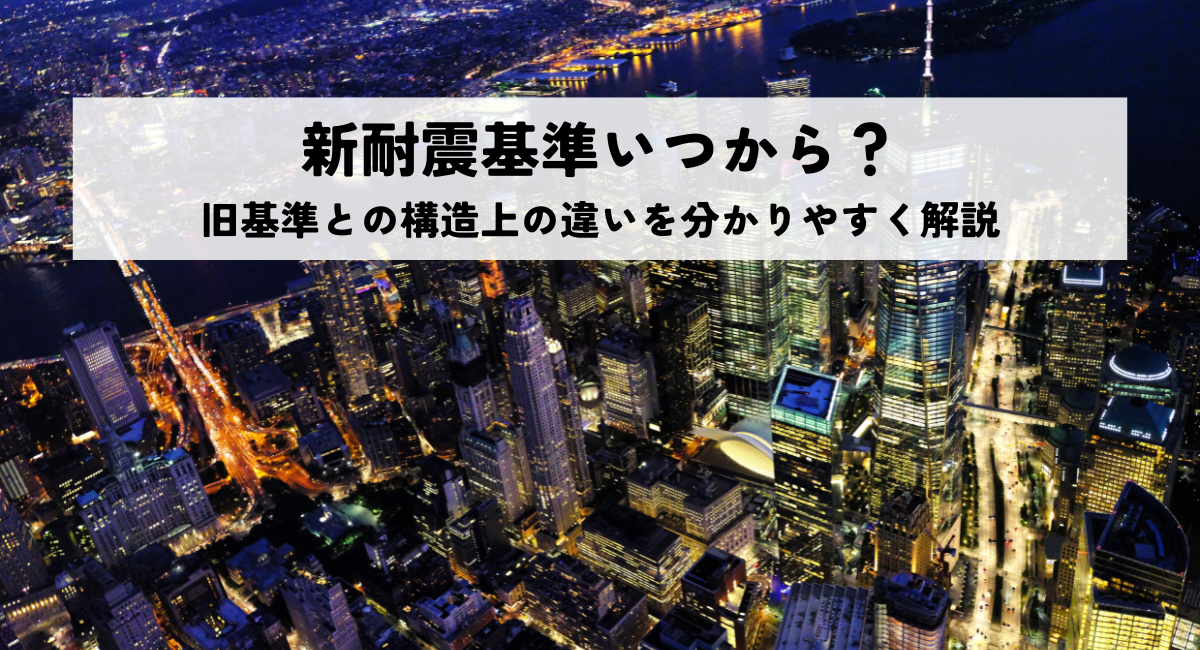
マイホーム購入は人生における大きな決断です。
多くの検討事項がありますが、近年増加する地震災害を鑑みると、建物の耐震性は特に重要なポイントと言えるでしょう。
安心して暮らせる家を選ぶために、耐震基準について理解を深めることは不可欠です。
特に、新耐震基準と旧耐震基準の違いは、住宅選びにおいて大きな影響を与えます。
今回は、その違いを分かりやすく説明します。
新耐震基準とはいつから?
新耐震基準の施行時期
新耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日から施行されました。
それ以前の基準は「旧耐震基準」と呼ばれ、1981年5月31日までに建築確認が完了した建物に適用されます。
建築確認日によって基準が変わる点に注意が必要です。
つまり、建築確認日が5月31日以前の場合、建築開始日(着工日)が6月1日以降であっても旧耐震基準が適用されます。
旧耐震基準との違い
旧耐震基準は、震度5程度の中規模地震を想定していました。
一方、新耐震基準は、震度6強程度の大地震にも耐えられるよう設計されています。
これは、大きな地震災害を経験した結果、基準が大幅に見直されたためです。
新耐震基準では、建物の倒壊を防ぎ、人命を守るための設計が求められます。
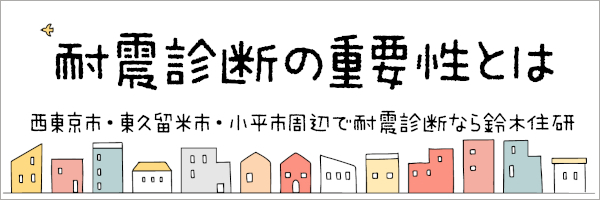
新旧耐震基準の構造の違い
建物の骨組みの違い
新耐震基準では、建物の骨組みとなる柱や梁の強度が大幅に向上しました。
旧耐震基準では、主に建物の自重を支えることに重点が置かれていましたが、新耐震基準では、地震による大きな力にも耐えられるよう、より強固な構造が求められます。
これは、部材の材質や断面寸法の変更、接合部の強化などによって実現されています。
耐力壁の配置の違い
耐力壁とは、地震の力を支える壁のことです。
旧耐震基準では、耐力壁の必要量はある程度規定されていましたが、その配置についてはそれほど厳しくありませんでした。
しかし、新耐震基準では、耐力壁の配置バランスが重要視され、建物の各部分に適切に配置されるよう、より詳細な設計が求められるようになりました。
これは、地震による力の偏りを防ぎ、建物の全体的な強度を向上させるために必要です。
接合部の違い
建物の骨組みを構成する部材同士の接合部も、新耐震基準では強化されました。
旧耐震基準では、接合部の強度が不足しているケースも見られましたが、新耐震基準では、接合部に適切な金物を使用したり、接合方法を工夫したりすることで、地震力による破壊を防ぐ対策が講じられています。
特に、柱と梁の接合部は、建物の耐震性に大きく影響するため、細心の注意が払われています。
耐力壁の配置バランス及び接合部の強化については、2000年(平成12年)に更に高められ現在に至ります。
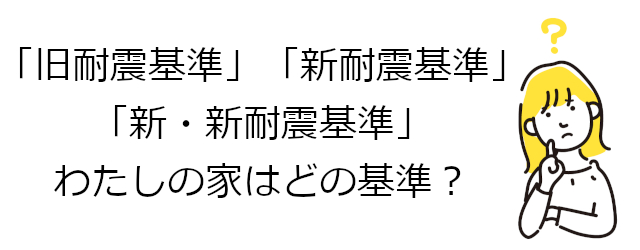
まとめ
新耐震基準は1981年6月1日から施行され、旧耐震基準と比べて地震に対する強度が大幅に向上しています。
新旧基準の違いは、骨組みの強度、耐力壁の配置、接合部の強度などに表れます。
マイホーム購入を検討する際には、建築確認日がいつなのかを確認し、耐震基準をしっかり理解することが重要です。
新耐震基準の建物であっても、地震による被害を完全に防ぐことはできませんが、旧耐震基準の建物と比較して、安全性が格段に向上していることは確かです。
安心して暮らせる家選びのため、ぜひこの記事を参考にしてください。
旧耐震基準の建物でも、新耐震基準以上(現行の基準)に耐震補強することが可能です。
まずは「無料耐震診断」から始めてみませんか?
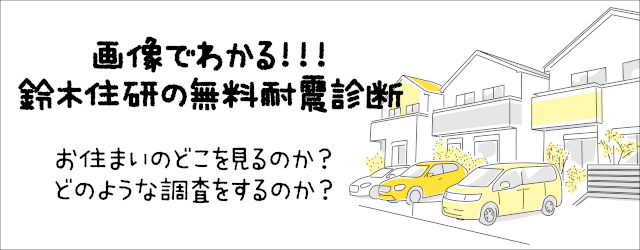
投稿者プロフィール
-
「鈴木住研」では、これまでに400棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。
経験豊富な東京都登録の耐震診断技術者(建築士)が責任を持って耐震診断を行なっております。
また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い補強工事も行なっております。
社員や協力会社と共に、お客様のご家族と住まいを長期にわたり見守り続けます。ぜひ安心して相談ください。